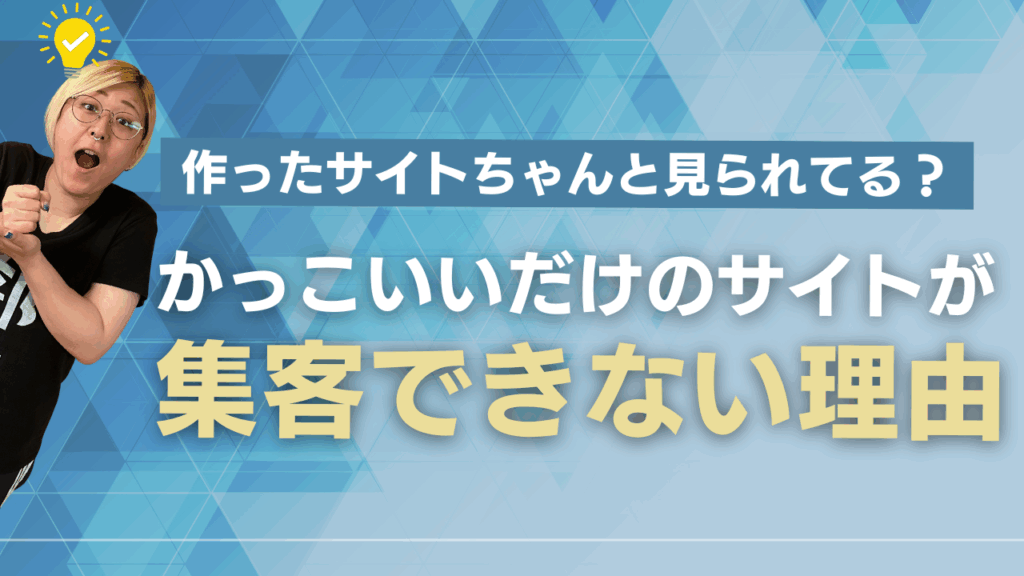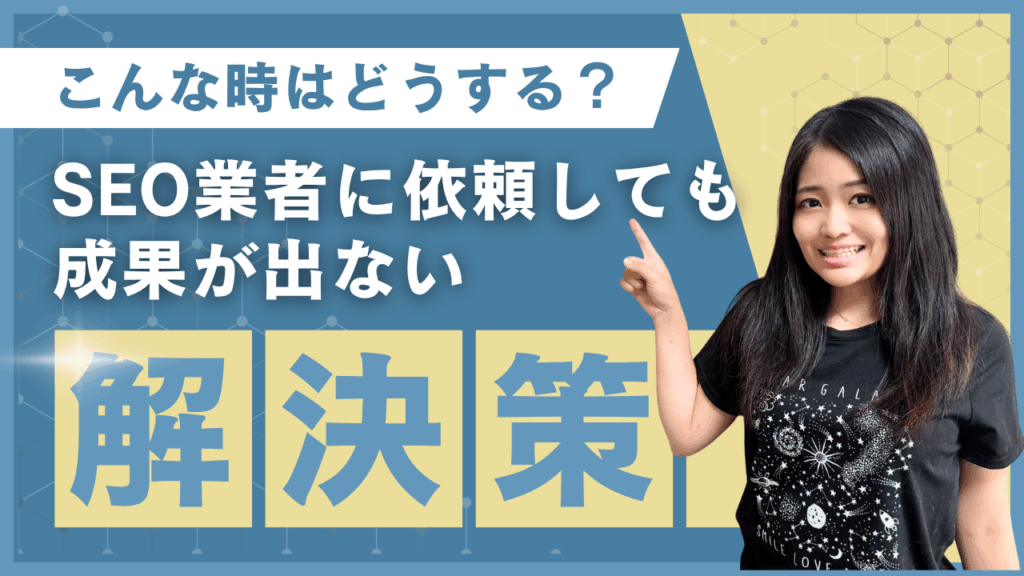Web制作とSNS運用はなぜセットで考えるべきか

「ホームページはあるけれど、集客が伸びない」「SNSは更新しているけど、反応が少ない」
このような悩みを抱える企業は少なくありません。
実は、WebサイトとSNSは切り離して考えるのではなく、“連携させる”ことで本来の力を発揮します。
本記事では、Web制作とSNS運用をセットで設計するべき理由と、その実践方法を解説します。
1. SNSは“導線”、ホームページは“受け皿”
まず役割を整理しましょう。
- SNS:拡散力・即時性・接点づくり
- ホームページ:信頼構築・情報の深掘り・最終アクション
つまり、SNSは「気になってもらうための入口」であり、
ホームページは「その関心を確信に変えるための場所」なのです。
SNSだけでは情報量や説得力が足りず、ホームページだけでは初動の接点が生まれません。
この2つは常に“セット”で設計する必要があります。
2. 一貫性があると“信頼される”
ユーザーがSNSからホームページへ移動したとき、印象がガラッと変わってしまうと不信感につながります。
- SNSでは親しみやすいのに、サイトが堅すぎる
- 投稿内容とサービス内容が噛み合っていない
- SNSに載っているキャンペーンがサイトには未掲載
このようなズレは、コンバージョン率の低下に直結します。
WebサイトとSNSは「世界観」や「トーン」を揃えることで、ブランドとしての一貫性を築くことができます。
3. SNS運用の目的を“制作段階から”決めておく
よくある失敗は、ホームページを作った後に「SNSもやった方がいいかも」と思いつきで始めてしまうこと。
これでは、連携が取れずチグハグな動線になってしまいます。
理想は、Web制作の設計段階でSNS運用の目的・導線を考慮することです。
- どのページにSNSリンクを置くか
- SNS投稿のどこからサイトに誘導するか
- キャンペーンやイベントをどう連携するか
最初から連携前提で設計することで、SNSもホームページも活きてきます。
4. 成果につながる「運用体制」を整える
サイトとSNSを連携させても、運用が止まっていては意味がありません。
特に中小企業では、以下のような問題が起こりがちです:
- SNS更新が属人化していて不定期
- ホームページの更新依頼に時間がかかる
- イベントの連携が直前でバタつく
こうした課題を防ぐためには、「誰が何を、どのタイミングでやるか」をあらかじめルール化することが必要です。
Web制作会社に運用も相談できる体制があれば、継続的に動かし続けることが可能になります。
まとめ|「つながっている設計」が成果を生む
SNSとホームページ、それぞれ単独では効果が出にくくても、つながりを持たせて設計することで、大きな成果を生み出します。
シュガープラスでは、Webサイト制作の段階からSNSとの連携を見据えた設計を行い、運用体制までサポートしています。
「今のSNSやホームページ、うまく活用できていないかも…」と感じている方は、ぜひ一度ご相談ください。