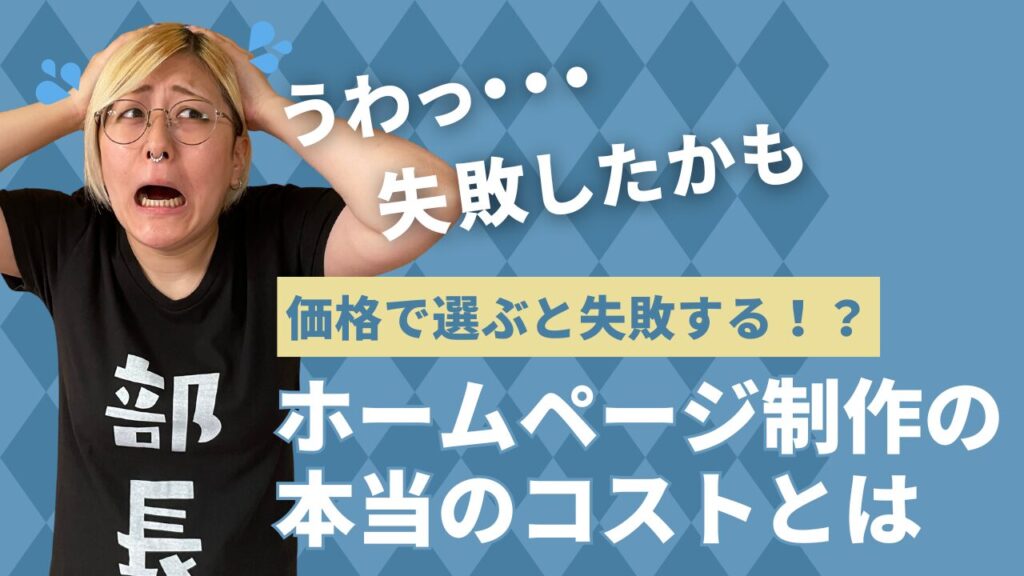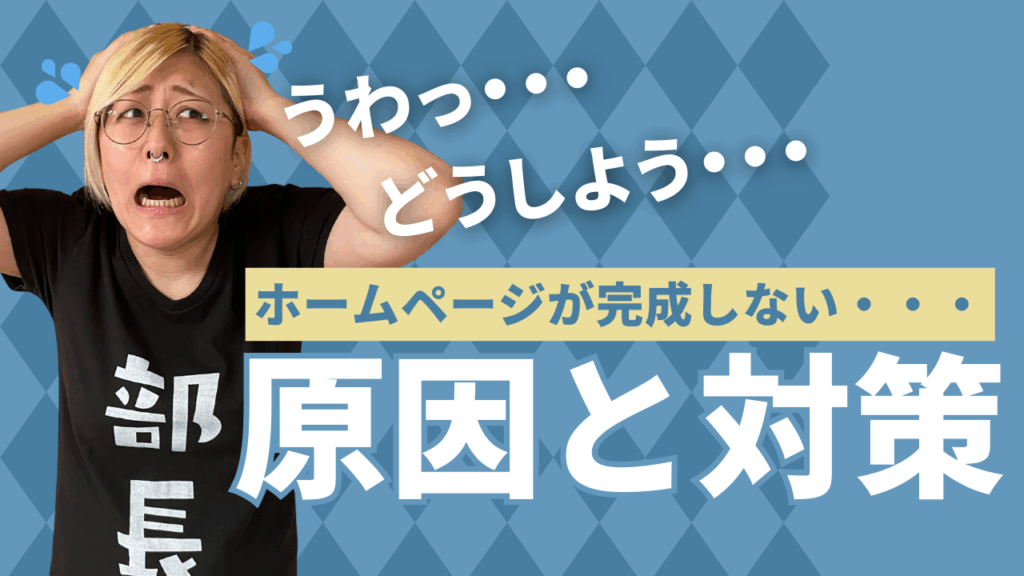ホームページは“誰のために”作るのか?目的のすり合わせで失敗を防ぐ

「ホームページを作りたいんです」とご相談を受けたとき、
私たちが必ず確認することがあります。
それは、“誰のために”ホームページを作るのか?ということ。
この視点が抜け落ちていると、公開後に「こんなはずじゃなかった…」という後悔に繋がりやすくなります。
ホームページの“目的”が曖昧だと、すべてがブレる
「とりあえず作りたい」「名刺代わりに必要」
そういった動機で制作がスタートすると、
誰に、何を伝えるか、どう動いてほしいかが不明確なまま進行してしまいます。
結果として、「見た目はいいけど成果が出ないサイト」になってしまうのです。
“社内のため”と“お客様のため”は違う
実は、ホームページには大きく分けて
①社内のために作る目的と、②お客様のために作る目的があります。
- ① 採用活動に使いたい
- ① 営業資料として使いたい
- ② お問い合わせを増やしたい
- ② サービスを比較検討中の人に選んでほしい
この目的のすり合わせをしないまま制作に入ると、内部の意見ばかりが優先され、ユーザー不在のサイトになってしまいます。
“誰が見るか”を具体的に描こう
目的がはっきりしてきたら、次は
「その目的を叶えるために、誰がサイトを見るのか?」を具体化します。
たとえば、こんな違いがあります:
| ターゲット | 求めている情報 |
|---|---|
| 初めて問い合わせを検討している人 | 実績、料金、信頼できるか |
| 他社と比較検討している人 | 違い・強み・納期など |
| 採用応募を検討している人 | 職場の雰囲気、仕事内容、福利厚生 |
誰が見て、どう行動してほしいかを明確にすることで、設計・構成・導線がぐっと良くなります。
「目的が1つに決めきれない…」場合は?
中小企業ではよくある話ですが、
ホームページに対して複数の目的があるケースもあります。
その場合は、「主目的」と「副目的」に分けて優先順位をつけることをおすすめします。
- 主目的:サービスへの問い合わせを増やす
- 副目的:採用情報を載せて、求人応募も受ける
このようにすることで、ページ構成やトップページの設計にも軸が生まれます。
まとめ|最初に“目的の言語化”を
ホームページ制作を成功させるための第一歩は、目的のすり合わせ。
そのためには、「誰が」「何のために」サイトを見るのかを具体的にすることが欠かせません。
デザインや機能はあとからでも変えられます。
ですが、“誰のために作るのか”を間違えると、根本からズレてしまいます。
制作パートナーと一緒に、はじめの一歩から言語化しておくことが、後悔のないホームページを作る最大のコツです。